自己紹介
新卒入社4年目のナガサカと申します。
私は現在、AWSの認定資格12冠(全種類)取得に向けて勉強中です。
AWS未経験からスタートし、働きながらコツコツと学習を積み重ねてきました。
最初に「ソリューションアーキテクト - アソシエイト」(以下SAA)を取得してから、
気がつけば現在11種類の試験に合格することができました。
この記事では、私がどのように勉強を進め、どうやってモチベーションを保ったのか、
実体験ベースで具体的にお話しします。 AWS資格に興味がある方、これから受験しようとしている方、
複数資格取得を目指している方の参考になれば幸いです。

AWS資格について
クラウドサービスのAWS(アマゾンウェブサービス)の認定資格試験です。
試験はパソコンで実施するCBT方式で行われます。
AWS認定資格は、2025年時点で12種類存在します。これらは大きく以下の4つのカテゴリーに分類されます。
■Foundational(基礎)
- Cloud Practitioner
- AI Practitioner
■Associate(アソシエイト)
- Solutions Architect – Associate
- Developer – Associate
- SysOps Administrator – Associate
- Data Engineer – Associate
- Machine Learning Engineer – Associate
■ Professional(プロフェッショナル)
- Solutions Architect – Professional
- DevOps Engineer – Professional
■Specialty(専門知識)
- Security – Specialty
- Advanced Networking – Specialty
- Machine Learning – Specialty

12冠取得しようと思い立ったきっかけ
私がAWSに初めて触れたのは新卒1年目の研修でした。最初はいろいろなサービスがあり、
説明を聞いても何がなんだか分からなかった記憶があります。
研修後、配属された最初の現場ではAWSサービスを使用していました。
研修で使用しなかったサービスも使用していたので早く戦力になろうと思い、
自分でAWSアカウントを作成し、いろいろなサービスを実際に利用して勉強し始めたのです。
最初に受験したSAAは、チーム内でも取得している方がいたため、自分の勉強の成果を測る意味で
取得を目標とし、新卒1年目の冬に合格することができました。
勉強するために資格について調べていた時、AWSの資格12個全てそれも2カ月という短期間で
取得したという方の記事を見て、当時は世の中には優秀なエンジニアの方もいるのだなと思い、
私には手の届かない存在だと感じたことを記憶しています。
学ぶなら全力で、いつかこの記事の方のようになろうと思い、業務をしながら勉強会などに
積極的に参加して学んでいきました。
本格的に「12冠目指せる」と感じたのは5個目の「DevOps Engineer - プロフェッショナル」を
取得したときです。その時すでに「ソリューションアーキテクト – プロフェッショナル」も取得していたので、
プロフェッショナルの試験は全て取得し、残りはアソシエイトと「もしかして行けるのでは!?」と思い、
その後約半年で6個の資格取得をすることができました!現在、残りの1つを取得に向けて、絶賛勉強中です。

学習時間の確保について
社会人だとどうしても過処分時間が限られるため、勉強時間の確保には工夫が求められます。
限られた時間の中で効率的に成果を出すためには、学習戦略の設計と、インプット・アウトプットの
バランスが鍵になります。 私は朝の時間を活用することで、学習時間を確保しました。
平日は業務に加えて残業や家事もあるため、夜の時間帯に十分な学習時間を確保するのは現実的に
難しいと判断し、生活リズムのを見直しを行い、早朝の時間を学習に充てる方針に切り替えました。
朝は外的な刺激が少なく、静かで集中しやすい環境が整っているため、高い質のインプットが可能です。
また、ランニングなどのルーティンと組み合わせることで、1日を前向きに始めることができ、
結果的に継続的な習慣として定着させることにも成功しました。このように、生活の中に学習を
「組み込む」ことで、意志力に頼らず持続可能な学習サイクルを構築することができました。

学習法について
正直に言うと、私は決して勉強が得意なタイプではなく、実際に試験に不合格になってしまった
こともあります。 当初は「自分の努力が足りないのだ」と考え、ひたすら独学で勉強を進めていましたが、
今振り返るとこれは非常に非効率なアプローチでした。というのも、既に多くの合格者が存在しており、
彼らがどのように学習を進めたのかを知ることは、学習戦略の精度を高めるうえで極めて有効だからです。
そこで私は考え方を切り替え、勉強会や周囲の合格者などを通じて、実際に合格された方々の学習法を
積極的に収集・分析するようにしました。実際の体験談には、教材の選び方から学習時間の使い方、
試験当日の戦略に至るまで、実践的かつ具体的な知見が詰まっており、自分の学習効率を大きく
引き上げるきっかけになりました。 私の場合、理解を深めるために、問題集を繰り返し解くことを重視し、
単に正解・不正解を確認するだけでなく、各問題に対して「なぜその選択肢が正しいのか」
「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を説明できるレベルまで掘り下げて考えるようにしました。
加えて、各サービスやアーキテクチャの構成を頭の中でイメージできるようになるまで何度も
復習を繰り返し、暗記ではなく「理解に基づいた判断」ができるようになり、応用力や初見問題への
対応力が大きく向上したと実感しています。
とはいえ、学習スタイルには個人差があるため、この方法がすべての人に適しているとは限りません。
自分に合った学習法を見つけるためにも、勉強会への参加や、他の合格者の体験談を
参考にすることをおすすめします。多様な視点に触れることで、自分にとって最も効果的なアプローチが
見えてくるはずです。
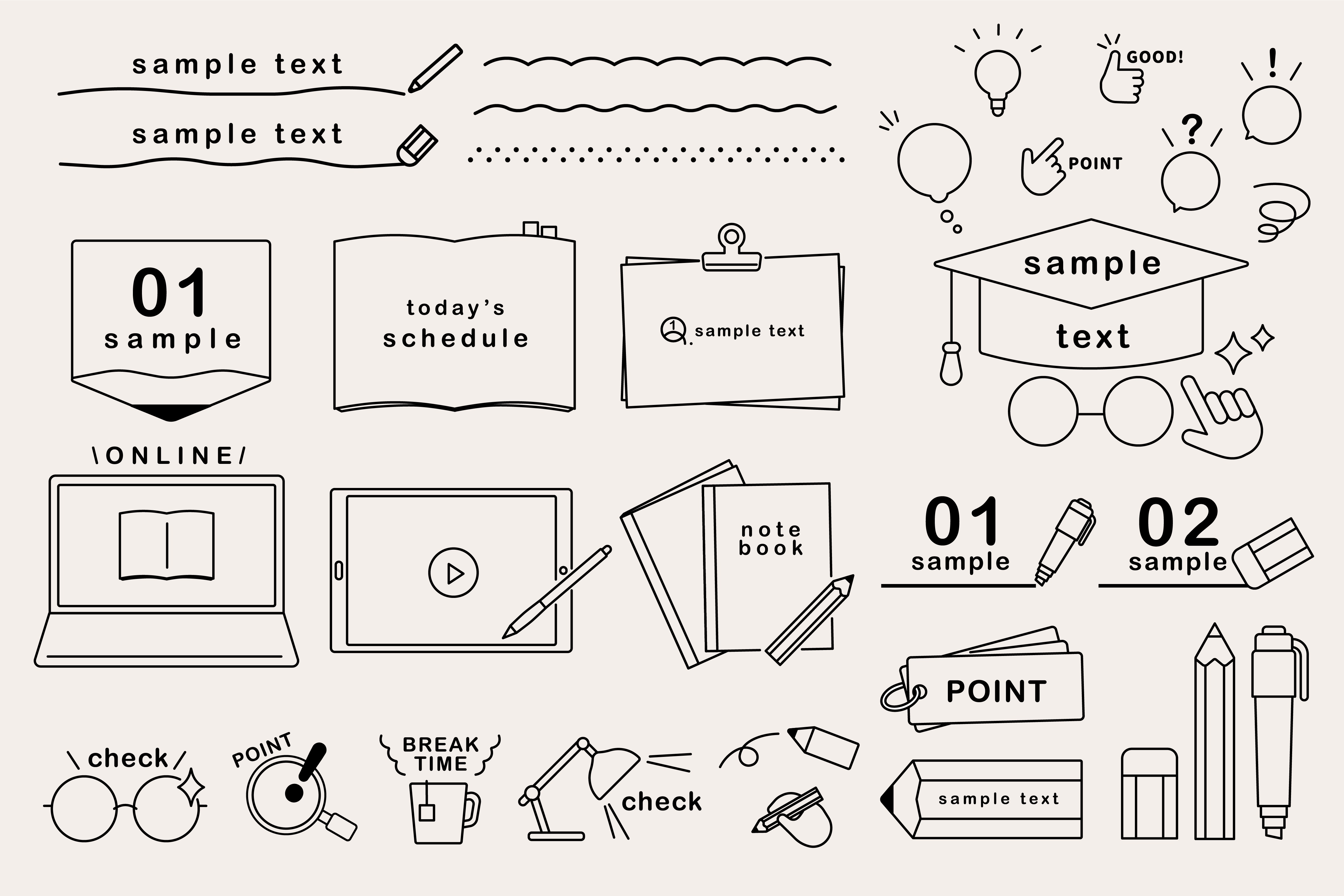
勉強会に参加して気付いたこと
勉強会に参加して気づいたことがあります。それは、同世代の参加者がほとんどおらず、
自分が最年少であることも少なくなかったという点です。
最初は少し緊張もありましたが、むしろそれが大きなチャンスになりました。
年上の参加者の方々は非常に親切で、こちらから積極的に質問すれば、実務経験を交えながら丁寧に
教えてくださいました。書籍やオンライン教材だけでは得られない、現場視点の実践的な知識や考え方に
触れることができたのは、大きな財産です。
また、意識の高い参加者たちと同じ空間に身を置くことは、モチベーションの維持にも非常に効果的でした。
「この人たちに追いつきたい」「もっと話についていけるようになりたい」という気持ちが自然と湧き、
学習を続ける推進力となりました。 積極的に行動することの大切さを実感することができました。

最後に
今回ご紹介した学習法や考え方は、AWS資格に限らず、他の資格にも応用できるものと思っています。
限られた時間の中で成果を出すための工夫や、モチベーションを維持するための環境づくりは、
どんな学びにおいても共通する重要な要素だと感じています。
これから学習を始める方、挑戦中の方の背中を少しでも押せるような内容になっていれば幸いです。



