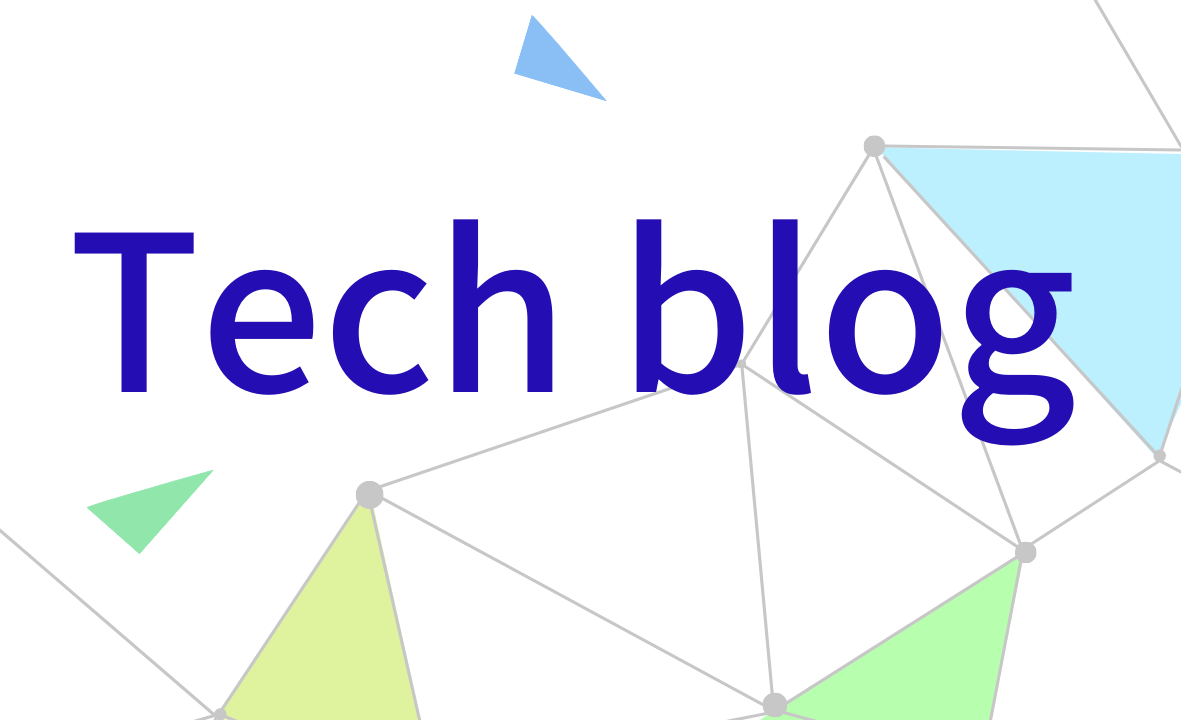始めに
はじめまして、エンジニアブログをご覧いただき、ありがとうございます。
アルティウスリンク株式会社に2022年新卒として入社し、4年目のFです。
私は現在APIとして基幹システムのデータをフロントシステムに提供するシステムを担当しております。
システムはAWS上に構築されており、画面を持つフロントシステムと、大量のデータを保有する
基幹システムの間に位置しています。
OracleからPostgreSQLへのデータベース更改および構成のリアーキテクト対応、
システムのマルチリージョン化、通常の維持保守対応や障害対応など、
インフラ担当として幅広く業務に携わっております。

現場で使用している技術内容について
チーム全体で使用している技術やサービス、ソフトウェアなどは多岐にわたるため、
今回は担当しているシステムや、個人的に気に入っているシステムの仕様などに絞って
お伝えできればと思います。
AWS系のサービスと機能について
R53ヘルスチェック
再掲となりますが、担当システムはフロントシステムにAPIとして、複数の基幹システムからの
データを共有する役割を担っています。そのため、データベースの可用性が非常に重要なシステムです。
加えて、1秒間のアクセス数は数千となるタイミングもあり、障害発生時に切り替えをスムーズに行えないと、
その間に多くのエンドユーザーに影響が及ぶとともに、システム上でも大量のアラートが
発生することになります。
そのような中で、データベースを意識した自動切り替えを実現するのが、R53のヘルスチェック機能です。
通常のヘルスチェックはエンドポイントに対するヘルスチェックのみで、あくまでアプリケーションを
ターゲットに対象としています。
担当システムでは、ヘルスチェックの宛先として独自作成したデータベースの特定テーブルを確認し、
そのアプリケーションの応答を返すように設定しています。データベースの応答に問題がある場合は
ヘルスチェックエラーとなり、東阪の切り替えを自動でできるような仕組みを実現しています。
EventBridge + SSM Automation/RUNCOMMAND
SSMは、運用にまつわるさまざまなことができるサービスです。
具体的には、EC2上のディレクトリに配置したシェルなどをAWSのマネジメントコンソールや
API経由で呼び出して設定を変更したりと使い方はさまざまです。
EventBridgeは、LinuxのCronのような設定をできるサービスで、時限でAWSサービスを利用したい場合に
活用するサービスです。これをSSMと組み合わせて使用することで、時限でのSSM呼び出しを可能にし、
運用の幅が広がります。また、OSに入らなくてもマネジメントコンソールからOS操作を可能にするため、
運用が手軽になります。
そんな、EventBridge + SSM Automation/RUNCOMMANDの組み合わせについてですが、担当システムでは
検証環境の自動停止起動などで利用しています。単にサービスを自動起動停止するだけであれば、
AutoScalingグループの利用などで対応可能ですが、使用可能な状態にするため、プロセスの起動などを
実施したい場合は、この組み合わせがおすすめです。この組み合わせを活用し、
お客様の検証環境の使用料金を年間数百万円削減し、クライアントに大きく貢献することができました。
検証環境の運用状況はさまざまな事情により、不要なリソースが削除されずに残っている場合があると
考えられます。定期的なコストエクスプローラーの確認をおすすめいたします。
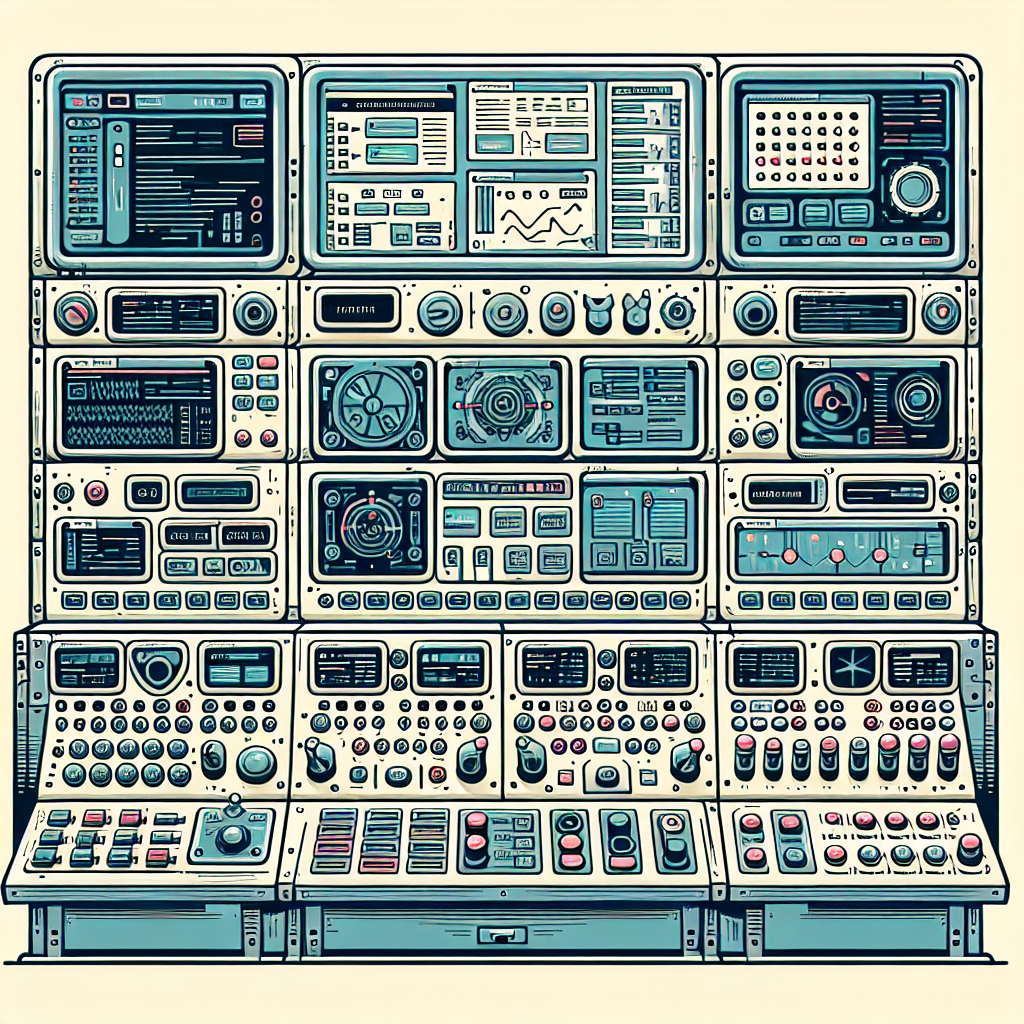
その他利用ミドルウェアについて
Oracle Golden Gate
こちらはAWSのサービスとは異なり、聞き馴染みのないサービスかもしれませんが、
担当システムにとって重要な要素の一つがOracleGoldenGate(以下GG)です。
概要としては、ソースと呼ばれる更新元のデータベースと更新先のデータベースである
ターゲットに同様のテーブルを用意し、必要なGGプロセスを起動することで、ソースのテーブルが
更新されるとターゲットにSQLが伝播され、ターゲットの方もリアルタイムで更新することが可能です。
担当システムは、基幹システムからのデータをバッチ処理で更新する方法と今回紹介したGG連携の2つで
システム内のデータベースが更新される仕様となっており、リアルタイム性が求めるデータには
GG連携を選択しています。概要にも記載した通り、ソースとターゲットのデータが揃っている必要があり、
揃っていないとGGプロセスがアベンドしてしまいます。
運用の際はデータの整合性に特に注意が必要であり、商用環境でのGGの設定変更やデータ投入に関しては
検証環境で基幹システムを含めたリハーサルを行う運用としいてます。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございました。
弊社はKDDIグループを中心に多様な現場を有しておりますが、私の就業先はAWSシステムを中心に
オンプレミスシステムまで管轄しており、幅広い技術に触れる事ができる環境となっております。
今回は使用している中でより思い入れがあるものに絞ってご紹介いたしましたが、
次回は他のAWSサービスや、より詳しいGGに関する説明などができればと思います。